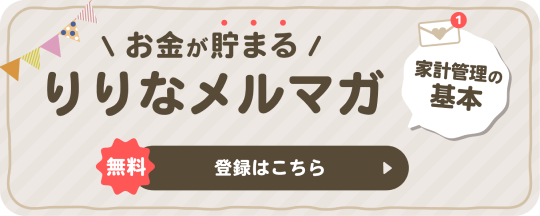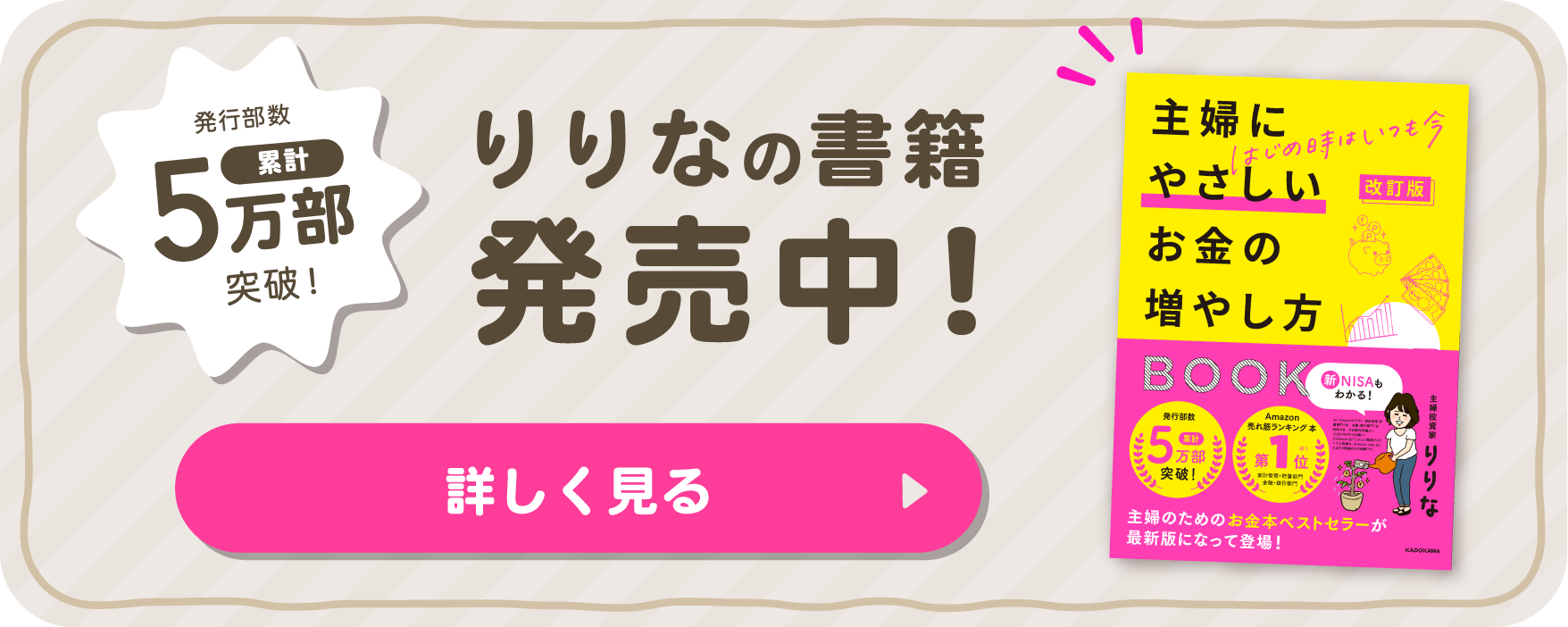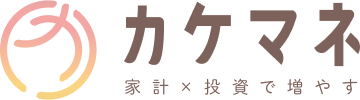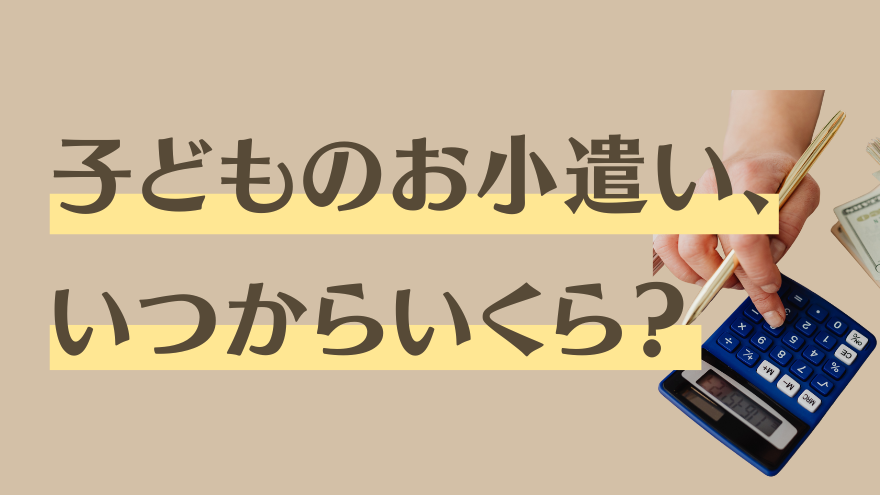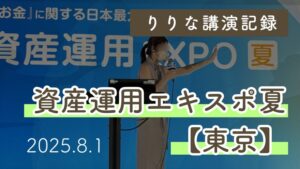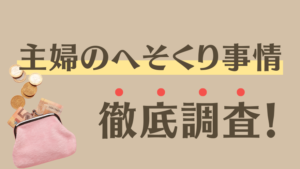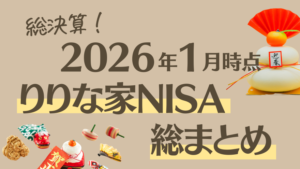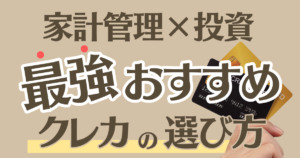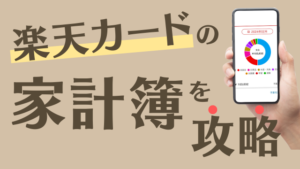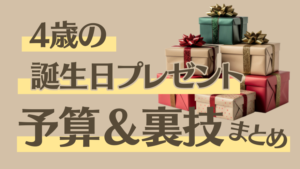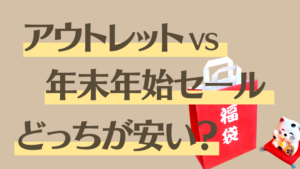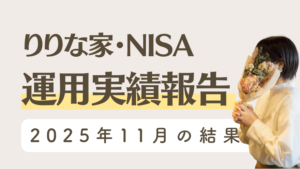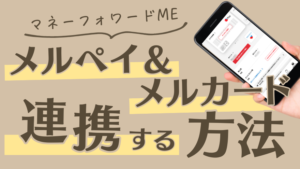子どもにお小遣いって、いつから渡せばいい?いくらが妥当?
そんな悩みを感じている方も多いのではないでしょうか。
お小遣いは、金銭感覚や自立心を育てる大切なステップ。
でも、年齢や家庭環境によって正解がないからこそ、迷ってしまいますよね。
そこでこの記事では、最新データをもとに学年別の平均額やメリット・デメリット、 わが家の実例まですぐに活用できる情報をギュッと詰め込みました◎
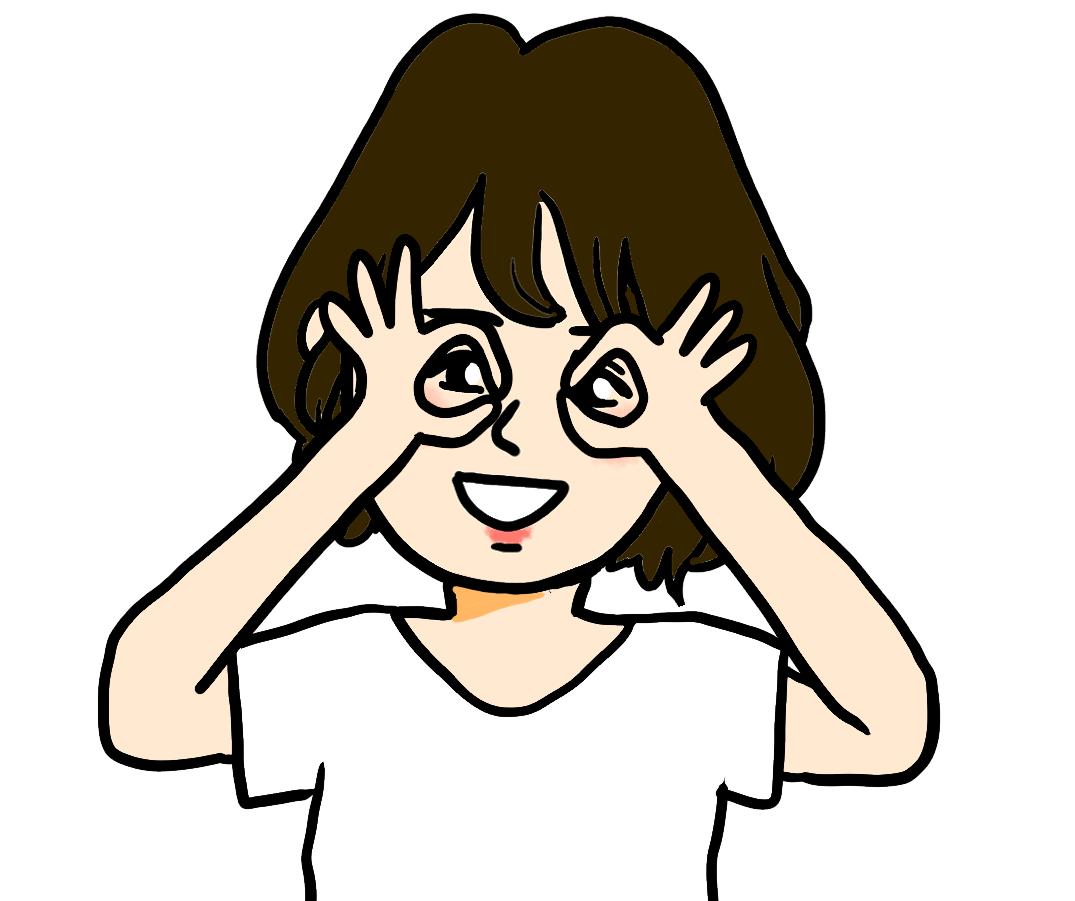
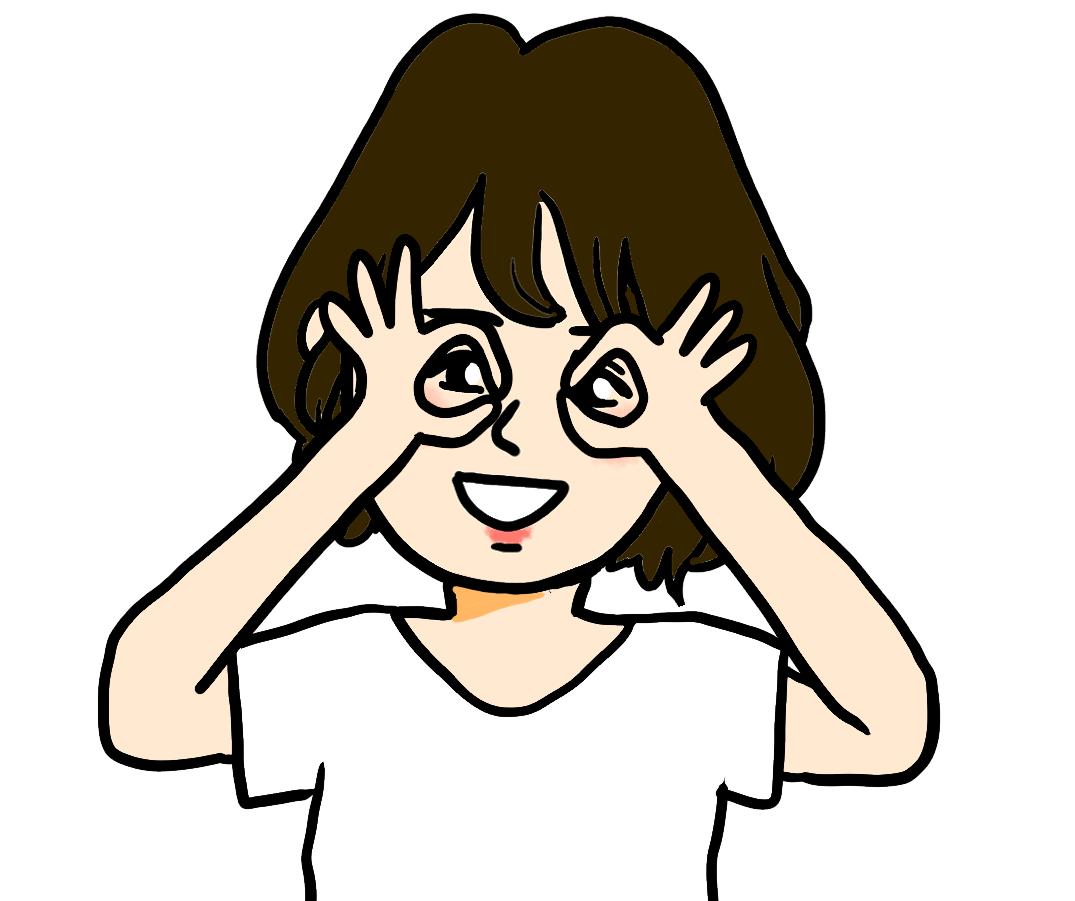
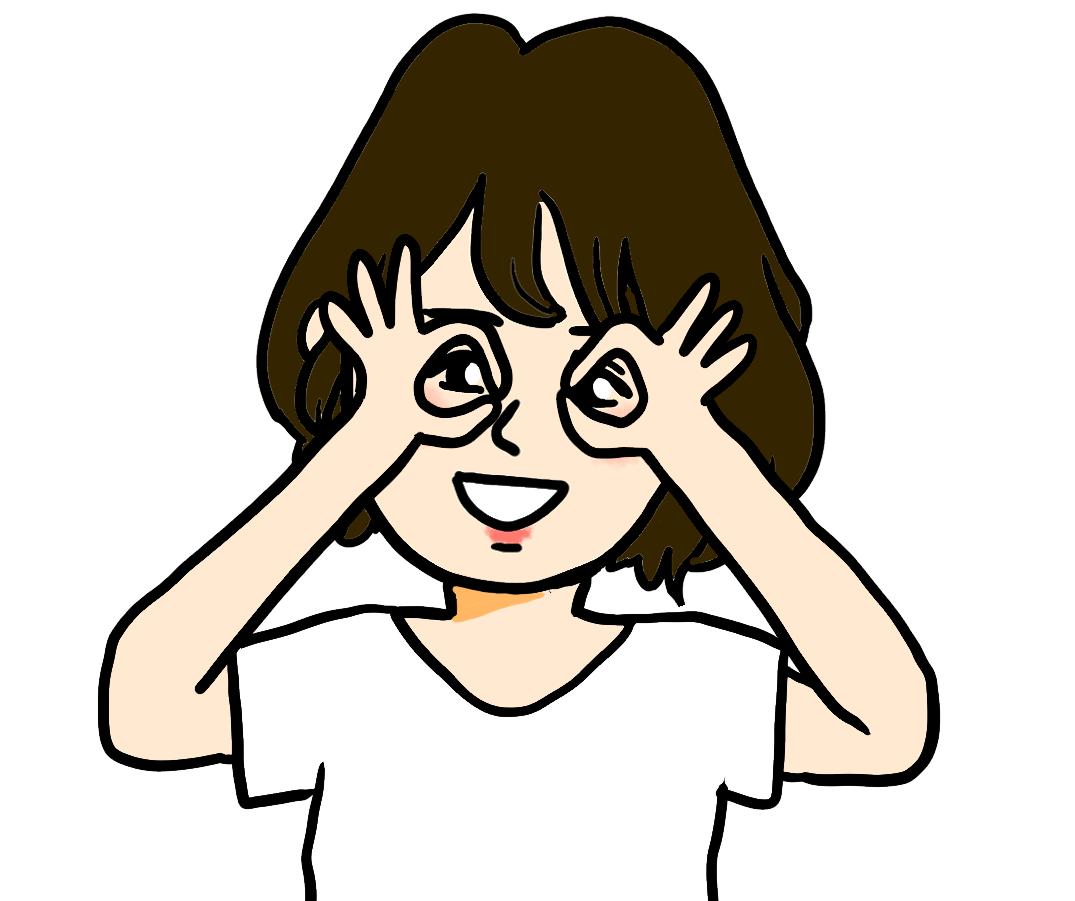
他の家庭はどうしてる?など少しでも気になる方は、ぜひ参考にしてみてね!
この記事を書いた人


りりな
- 結婚5年で資産3,000万円を達成。投資診断士/資産運用検定2級を取得。
- 日本テレビ「DayDay」、フジテレビ「Mr.サンデー」/テレビ朝日「なっ得!マネーの先生」等へ出演。
- Instagramフォロワー数29.4万人超。主婦にやさしい家計管理×投資情報を発信中。
- SBI証券・マネーフォワードのセミナーや資産運用EXPO、大学の講義等へ講師として登壇。ほか、各証券会社メディア・雑誌・ラジオ番組など多方面へも出演。
- 著書「主婦にやさしいお金の増やし方BOOK」累計5万部を突破!
この記事を書いている私は、投資歴8年以上です!失敗も経験しながら、主婦でもできる堅実な資産運用をしています!将来になんとなく不安がある・・と言うあなたに、分かりやすく資産運用の方法をお伝えしますね!
子どもにお小遣い、いつからどのくらい渡してる?
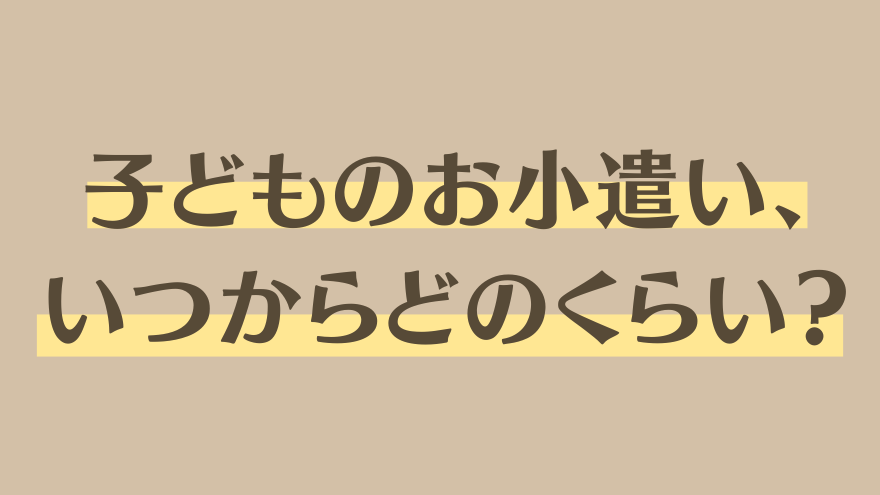
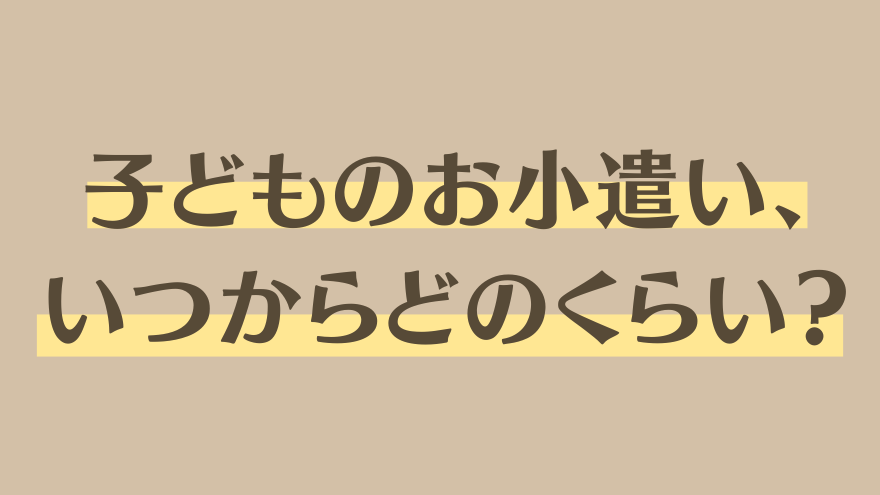
まず結論から行きます!
ベネッセ教育情報サイトの調査によると、小学生の約60%が月々お小遣いをもらっており、 中学生では約75%まで増加しています。
また、年齢ごとに必要な金銭感覚や使い道も変化するため、お小遣い額は学年が上がるごとに段階的に増えているのが一般的なようです。
学年別の平均額は?【2024年最新データ】
| 学年 | 平均月額 |
|---|---|
| 小学1〜2年生 | 500〜1,000円 |
| 小学3〜4年生 | 1,000〜1,200円 |
| 小学5〜6年生 | 1,500〜2,000円 |
| 中学生 | 2,000〜3,000円 |



子どもの金銭教育としてお小遣い制度を取り入れる家庭が増え、 早い段階から「お金って何?」を学ぶきっかけになってるみたいです◎
お小遣い制のメリット・デメリット
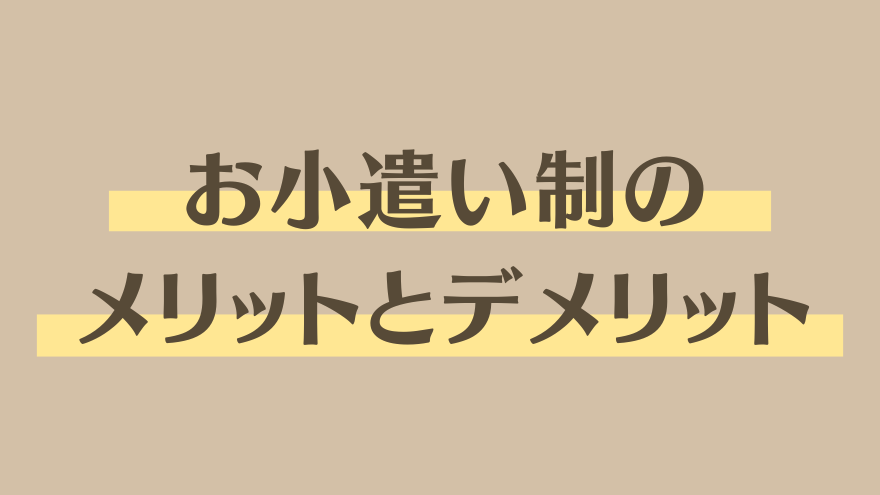
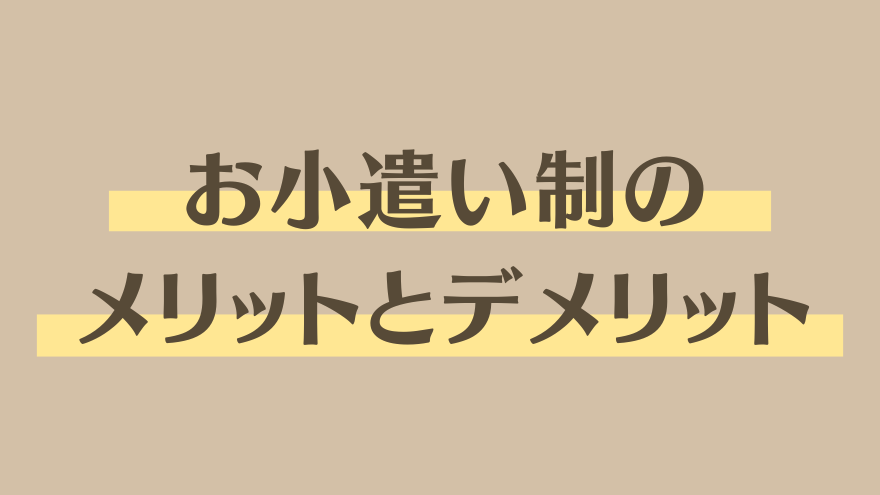
お小遣い制を導入すると、子どもにも家庭にもいい影響がある反面、注意したい点もあります。
メリット
- 金銭感覚が身につく
→限られた額の中でやりくりする経験から、「欲しいものにはいくら必要?」を学べます。 - 自己管理能力が育つ
→支給日や使い道計画を立てることで、計画性や責任感が養われます。
一方、デメリットも💦
- 家計の負担になる可能性
→子の人数が増えたり、金額設定が高額になると家計に影響が出てきます。 - 誤った価値観のリスク
→使い道を放任しすぎると、「お金はあるだけ使ってしまえ」という考えを持つ場合も。
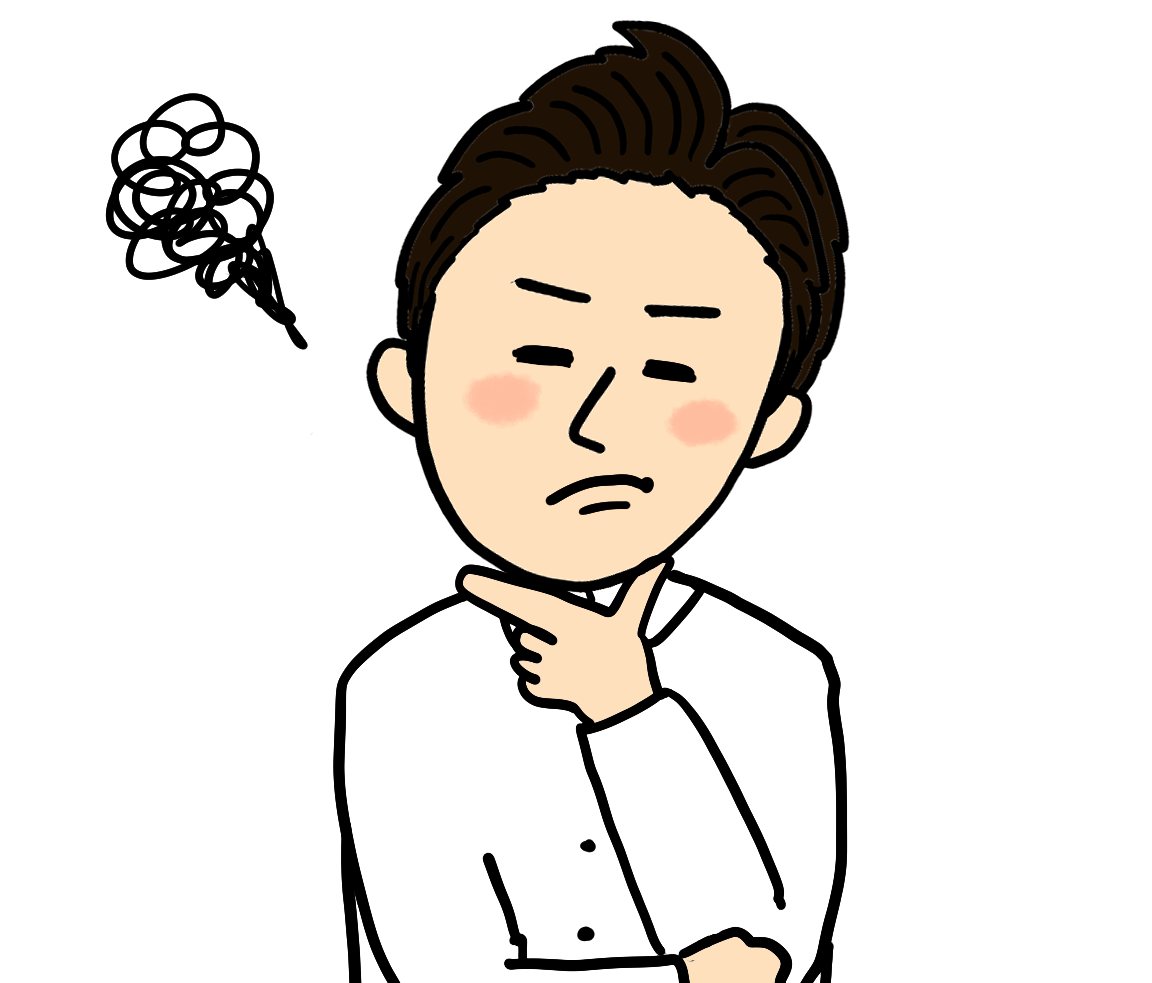
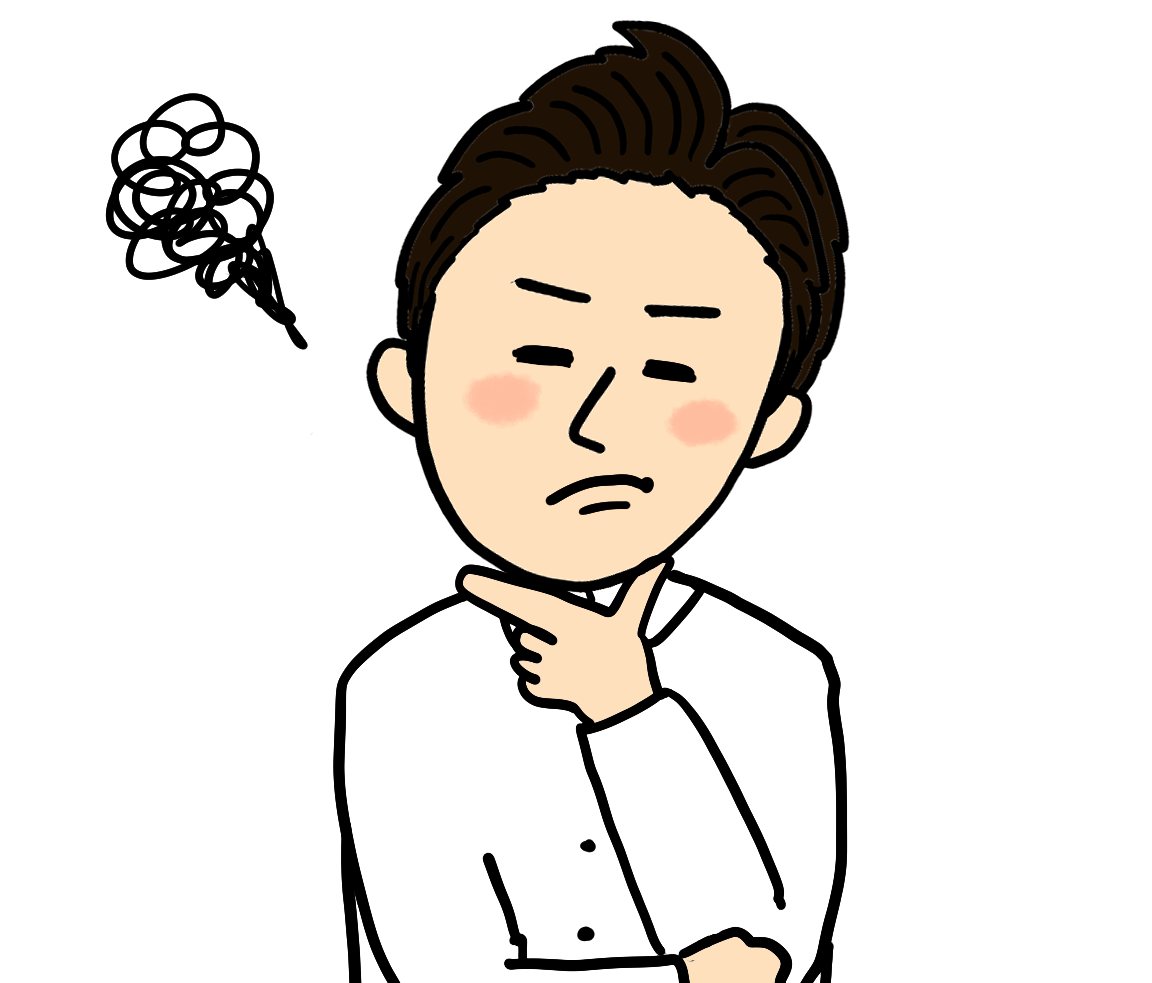
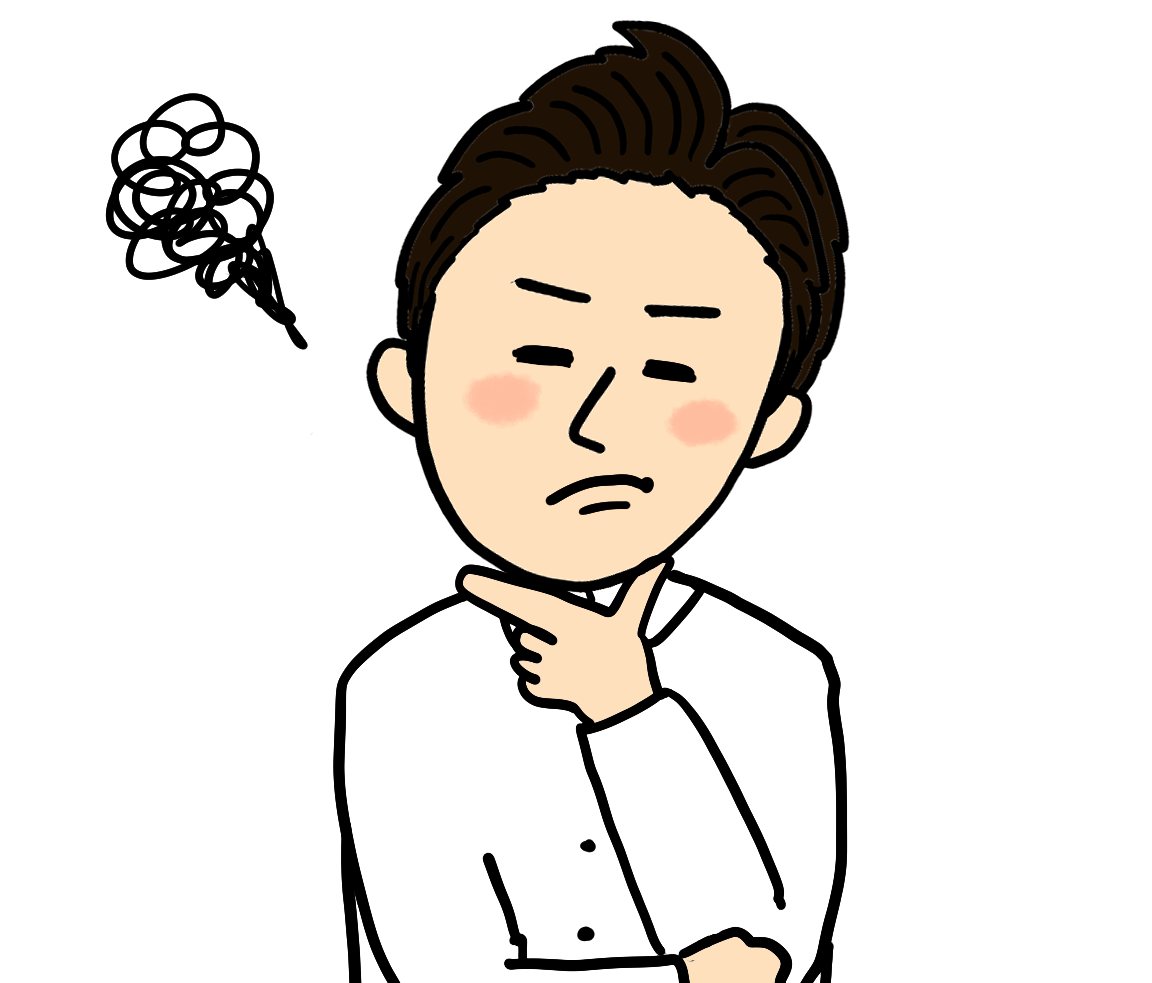
子供からすると嬉しいお小遣い制度だけれど、親としては、渡す金額や使い道に口出しするかは悩ましい問題だね!
「子どものお小遣いの金額」決め方3パターン【実例あり】
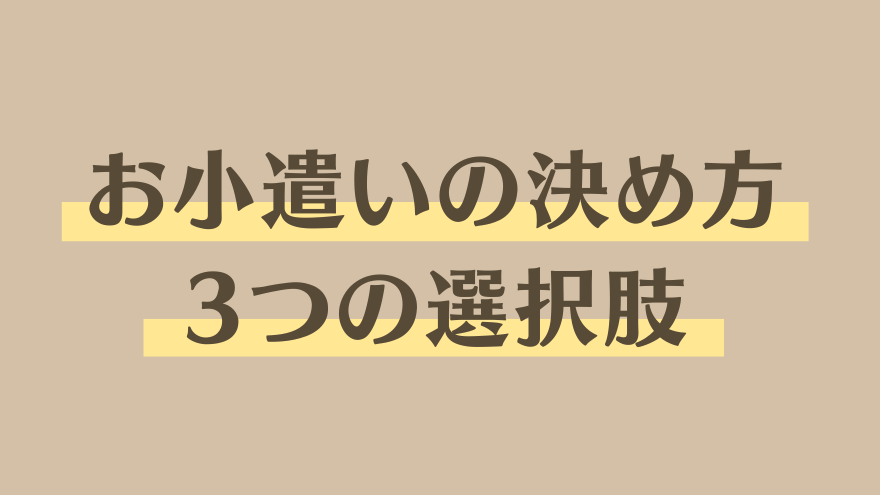
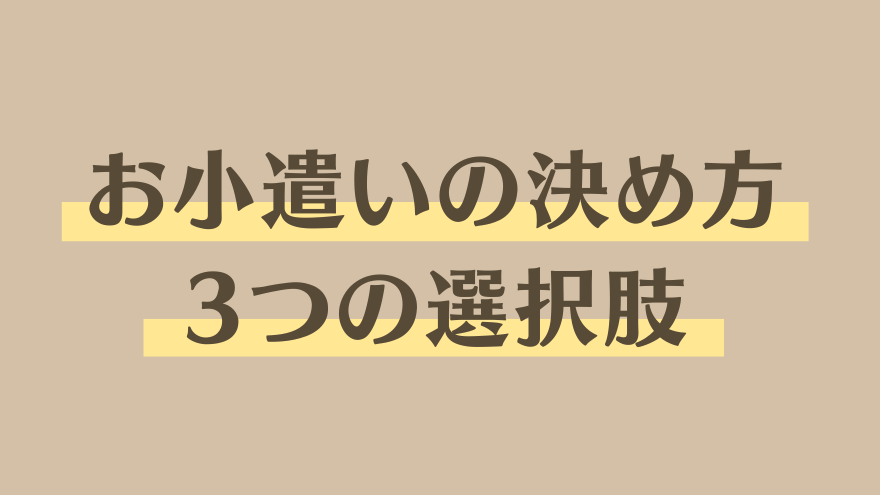
渡す金額に迷ったときは、以下の方法を参考にしてみてください。
①年齢×100円方式
一つ目は、年齢に100円をかける計算方法です。
例えば、5歳→500円、10歳→1,000円など…。
年齢と連動するので、シンプルで双方ともに分かりやすいというメリットがあります。
掛ける金額は、それぞれご家庭の価値観によって変えてみて下さい。
②一律金額方式
二つ目は、一律で渡す方法です。
兄弟姉妹がいる場合は不公平感を避けるため、全員「1,000円」など一律に設定するのがおすすめです。
③ 目標額設定方式
三つ目は、子供と目標金額を決める方法です。
子どもと一緒に「何に使いたいか」を決め、 「新しいおもちゃが欲しいから1,500円貯めよう」など、目的が明確になることで貯金のモチベーションが高まります。



どれか一つ!ではなく、自分たちに合ったルールを組み合わせてみてもOK◎
お小遣いにルールは必要?【家庭での工夫】
子供への渡す金額が決まったら、渡す前にしっかりとルールを話し合っておくことも忘れてはいけません。
- 支給日や金額は?
→ カレンダーに記入し、専用の封筒やアプリで共有する。 - 友達同士の貸し借りは?
→ トラブル防止のため、家族ルールに明記しておく。 - 無駄遣い時の対応は?
→ 口出しはせず、使った後に「どうだった?」と振り返る機会を設ける、など



一緒に決めることで、家族とのコミュニケーションも増えるよね♪
子どものお小遣いは現金とキャッシュレス、どっちがいい?
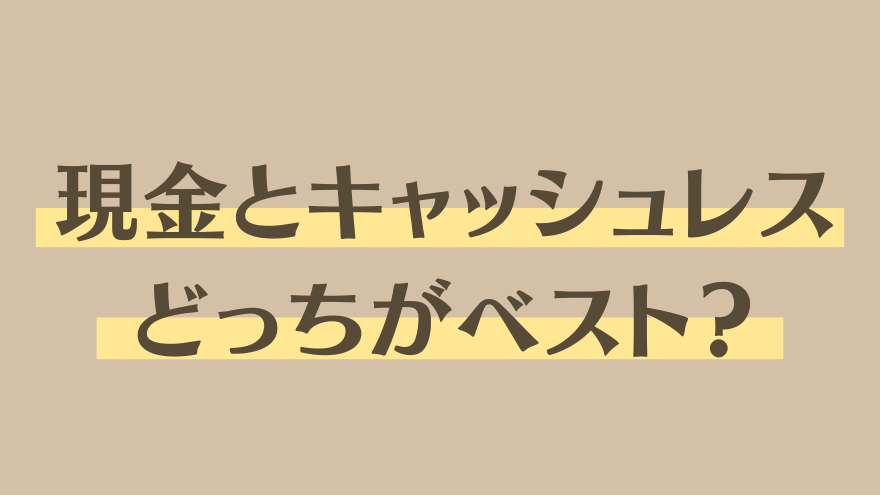
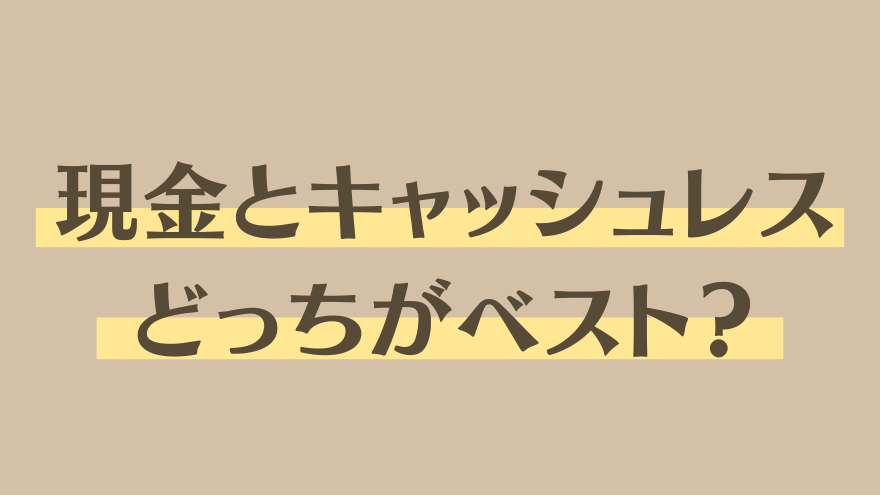
また現代では、キャッシュレス決済で支払うことも多く、現金を持ち歩かない方も増えてきました。
それに伴い、お小遣いを渡す方法も、現金派とキャッシュレス派の二つに分かれているみたいです。
- 現金 → 手軽で分かりやすい反面、使いすぎを把握しにくいことも。
- キャッシュレス(楽天Pay・PayPayなど)→ 残高履歴で支出を見える化しやすいが、使い過ぎに注意。
子供が大きくなりスマホを持たせるようになると、「キャッシュレスで送金する」という選択肢もありかもしれません。
わが家のお小遣いルール・実例と気付き
ちなみにわが家では、お出かけの際に子どもに現金500円ほどを渡し、使い道や管理は子ども自身に任せています。
ただ、今の物価高の時代500円では遊べない場面も多い…。そのため、インフレに応じて金額の見直しが必要だと感じてきています。



子どもたちが楽しめる範囲を考えると、額面以上の調整が求められるかも。。
とはいえ、あまりに多すぎてもお金の価値が分からなくなってしまうため、どこまで渡すかはやはり悩みどころですよね。
ただ基本的に私は、子どもが欲しいものに対しては「口出ししない」方針です。
まだ4歳ということもあり、これから成長とともにお小遣いルールは変わっていくかもしれません。
正解がないことだからこそ、試行錯誤してベストな方法を探していこうと思っています。
まとめ|家庭ごとのお小遣いルールをつくろう!
お小遣いは「正解」がないからこそ、子どもと一緒に考え、家庭ごとのベストを見つける楽しみがあります。
今回の目安をヒントに、
使う側も渡す側も納得できるルールを作るきっかけになると幸いです!



親子のコミュニケーションを深めながら、楽しく金銭教育を進めましょう!