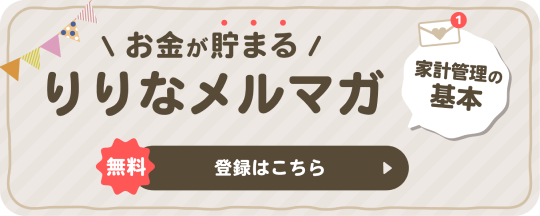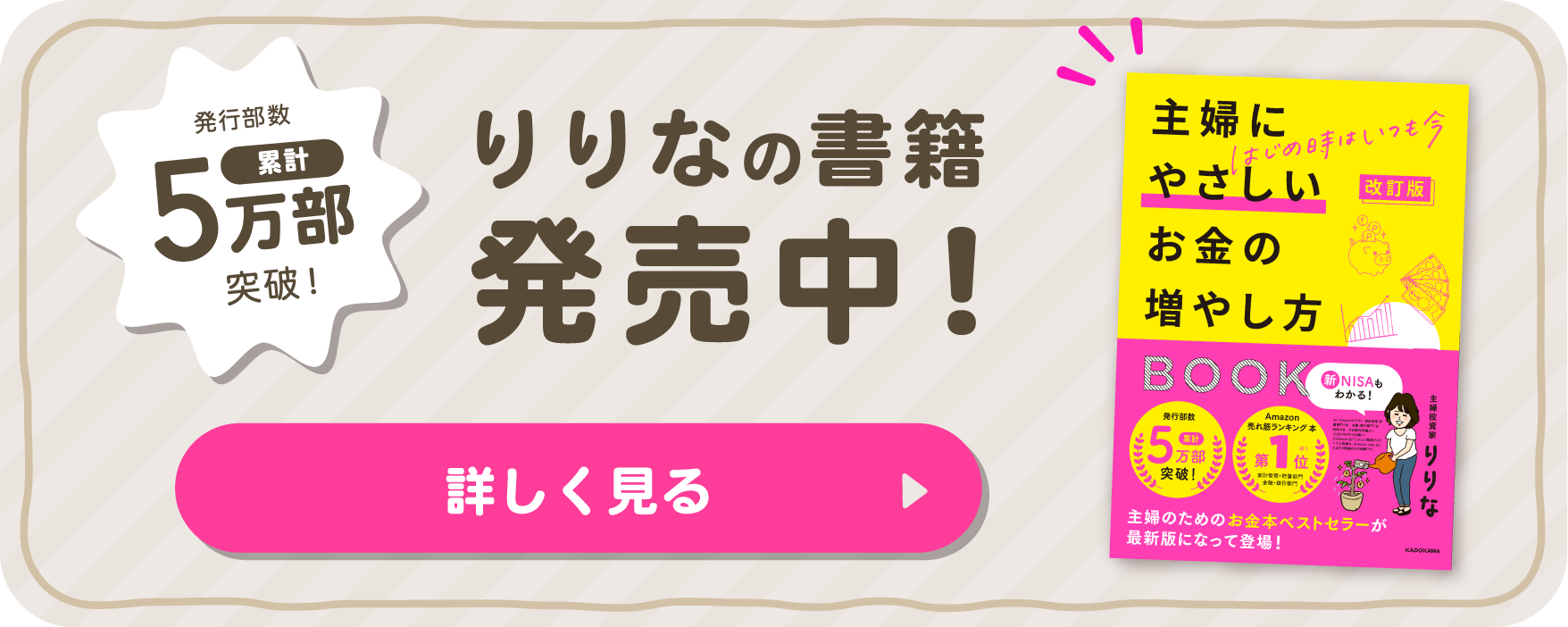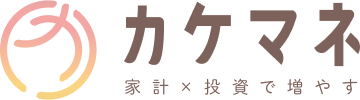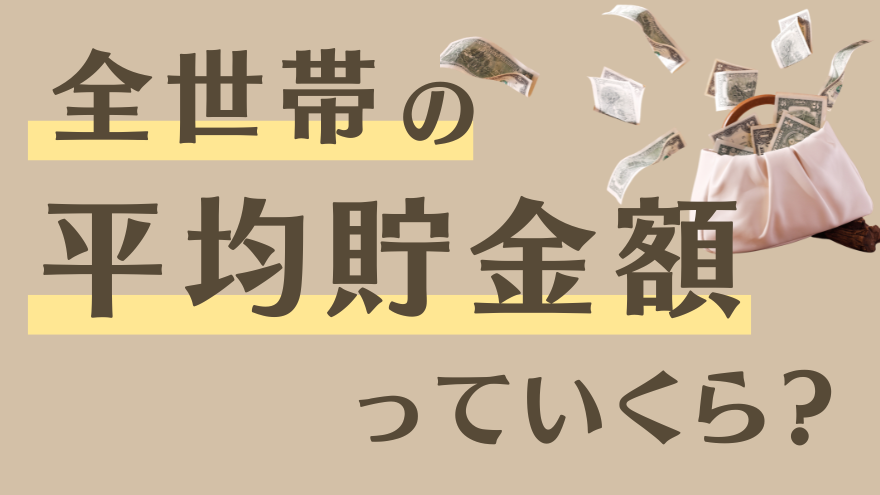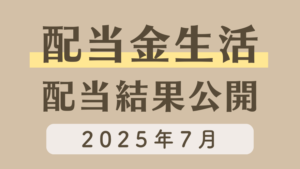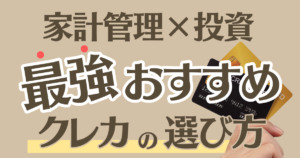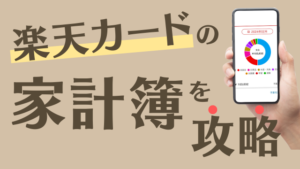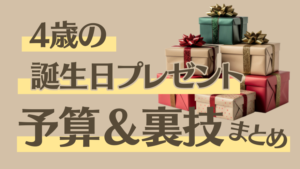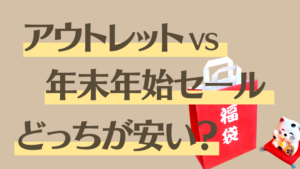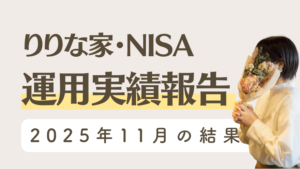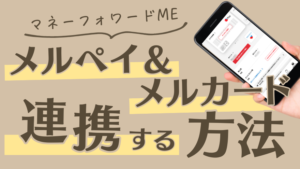「みんな、いくら貯金してるんだろう?」
ふと気になって検索したこと、ありますよね。
平均の金額を見て、安心したり焦ったり…。でも実は、その「平均貯蓄額」って、ちょっとややこしいんです。
というのも、調査によって対象が違ったり、単身世帯と二人以上世帯で数字が別だったりするので、正確に理解しないと迷子になってしまいます。
そこで今回は、最新のデータをわかりやすく整理して、
- 年代、世帯別の平均貯金額
- 毎月皆どのくらい貯金しているのか
- 無理なく貯めるための秘訣
などなど…自分の今の位置やこれからの目安が見えるようにまとめてみました!



読み終わる頃には、平均に振り回されなくていい理由がちゃんとわかる内容にしてみたよ✨
少しでも参考になると嬉しいです!
この記事を書いた人


りりな
- 結婚5年で資産3,000万円を達成。投資診断士/資産運用検定2級を取得。
- 日本テレビ「DayDay」、フジテレビ「Mr.サンデー」/テレビ朝日「なっ得!マネーの先生」等へ出演。
- Instagramフォロワー数29.4万人超。主婦にやさしい家計管理×投資情報を発信中。
- SBI証券・マネーフォワードのセミナーや資産運用EXPO、大学の講義等へ講師として登壇。ほか、各証券会社メディア・雑誌・ラジオ番組など多方面へも出演。
- 著書「主婦にやさしいお金の増やし方BOOK」累計5万部を突破!
この記事を書いている私は、投資歴8年以上です!失敗も経験しながら、主婦でもできる堅実な資産運用をしています!将来になんとなく不安がある・・と言うあなたに、分かりやすく資産運用の方法をお伝えしますね!
2024年の平均貯蓄額は?実は“二つの調査”がある
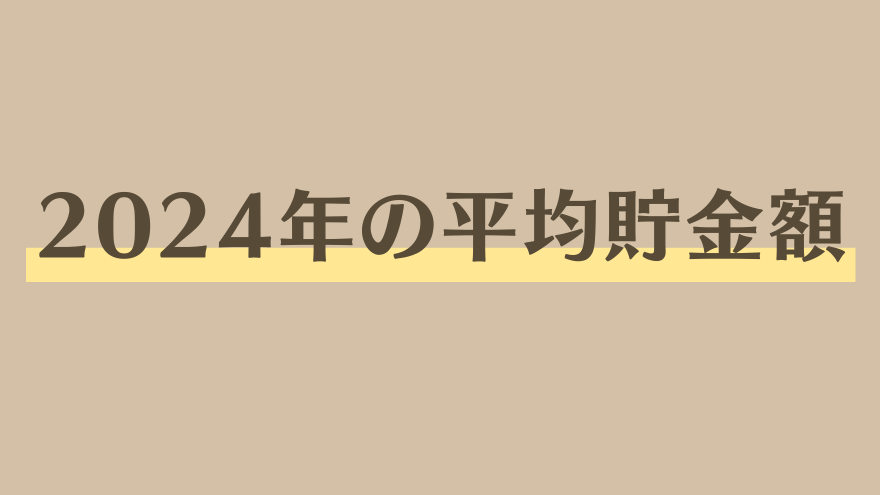
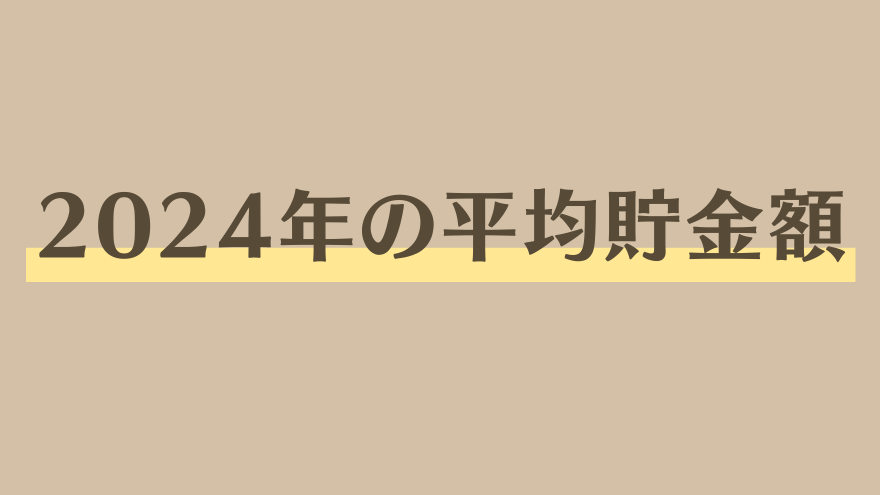
まずは、最新の「平均貯蓄額」をチェックして見ましょう。
総務省の家計調査によると、2024年の二人以上の世帯の平均貯蓄額は1,984万円。
これは前年比で4.2%増えていて、過去最高の水準です。
| 平均貯蓄現在高(貯蓄残高) | 1,984万円(前年比 +4.2%/+80万円) |
| 中央値(貯蓄保有世帯) | 1,189万円 |
貯蓄が増えているその背景には「コロナ後の生活防衛意識」や「物価高への備え」などといった可能性も考えられます。
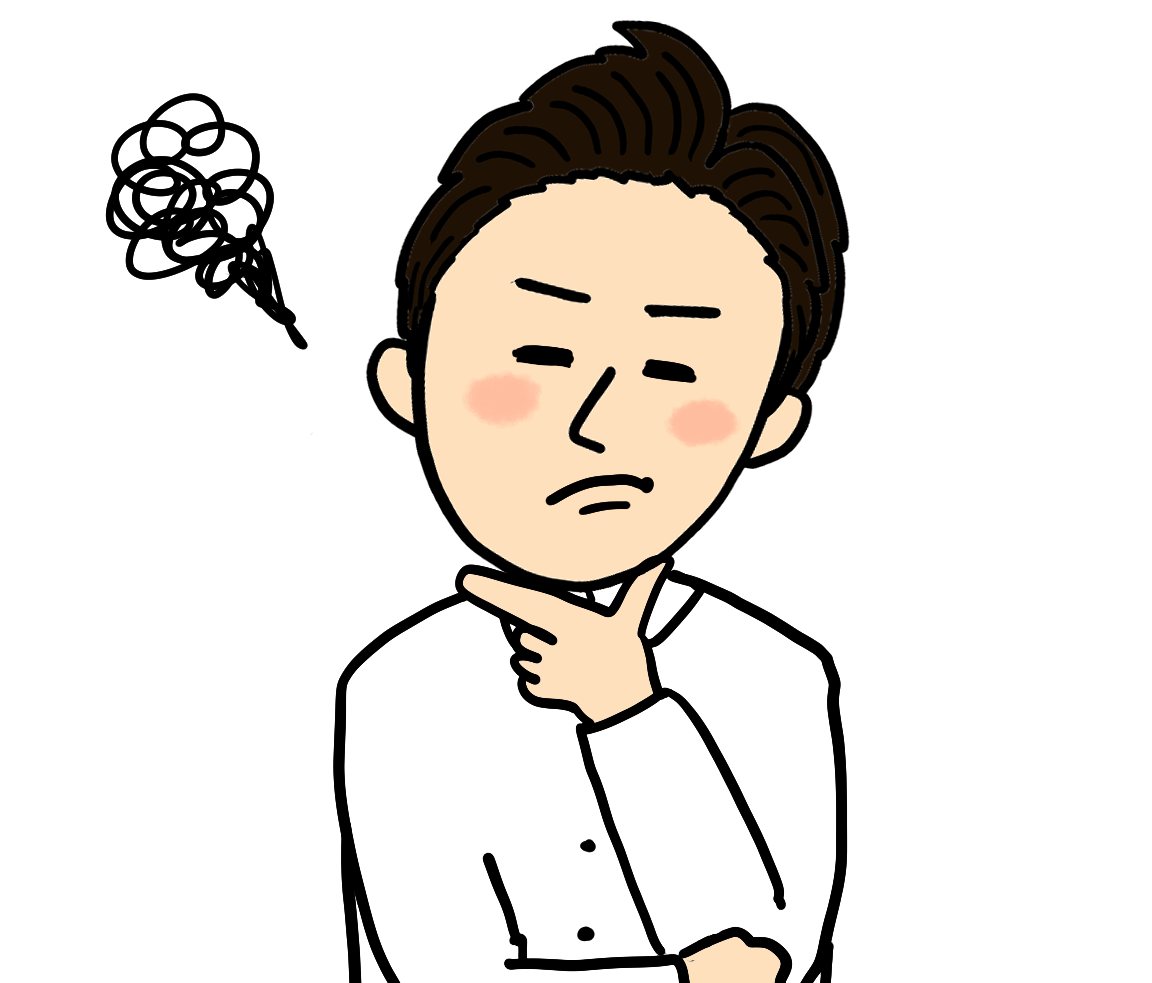
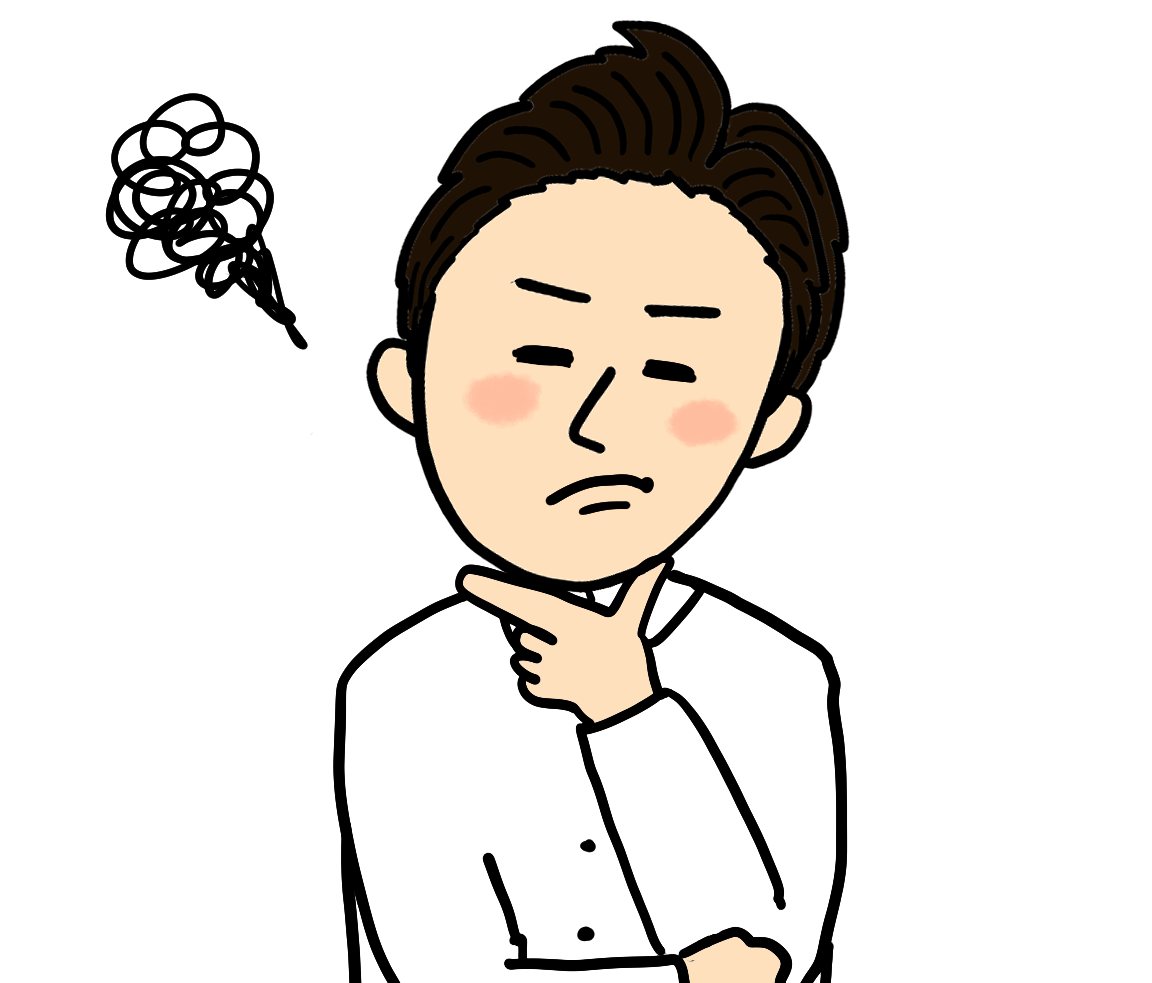
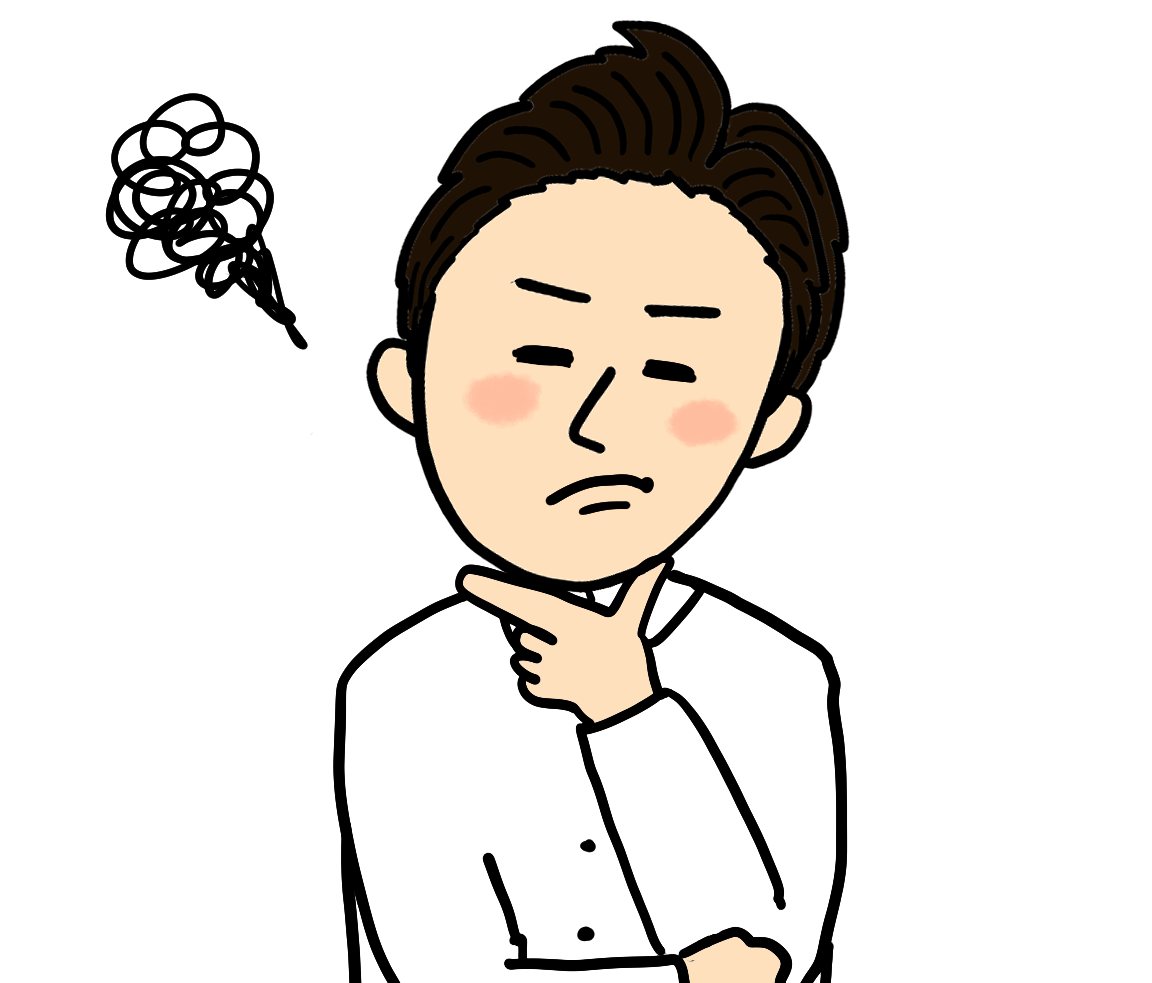
ただし、中央値は1,189万円。平均とかなり差があるね。
データをよく見てみると、平均値と中央値との差が大きいため、多くの世帯は平均を下回っています。
さらに、この家計調査は「二人以上世帯」限定という点に注意です!
一方で、単身世帯のデータではJ-FLEC(金融経済教育推進機構)の調査されていて、こちらの情報では、単身と二人以上を分けて公表しています。
つまり、「全世帯の平均」という1つの正解は存在せず、目的や自分の世帯構成に応じて、調査データを使い分けることが重要なことが分かります。
年代・世帯で、自分の位置を見てみよう
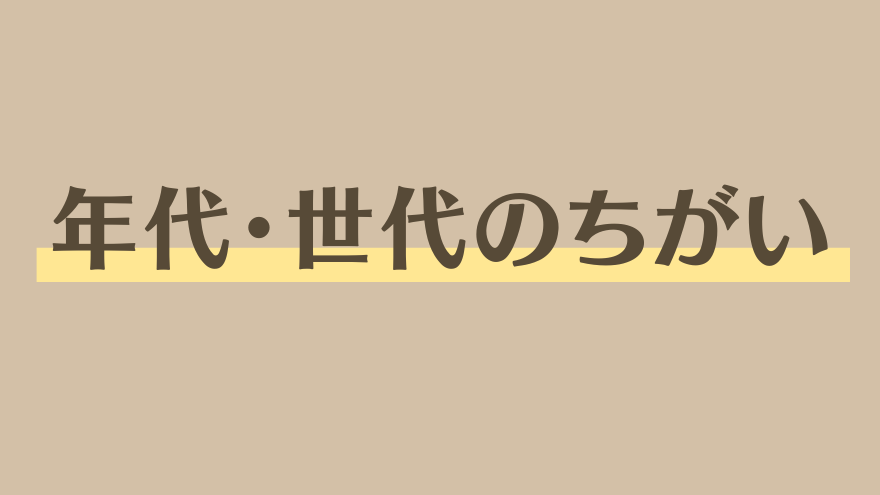
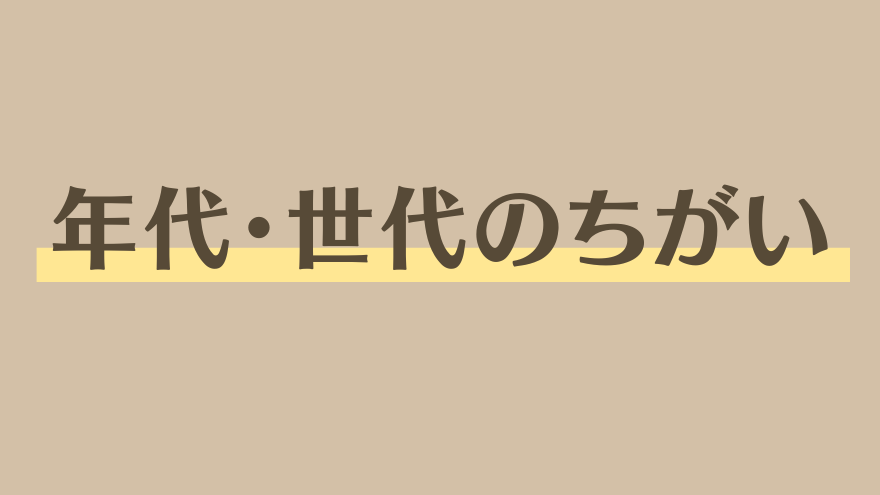
続いて、自分の貯金が多いのか、少ないのか…。最新データから、自分の立ち位置を見つけていきましょう!
以下は、2024年時点の主なデータです。(金融資産保有世帯)
- 二人以上世帯:平均 1,833万円/中央値 780万円
- 単身世帯:平均 1,497万円/中央値 500万円
また、年代別の中央値はこのような結果でした。
| 年代 | 平均貯蓄額 |
| 20代 | 171万円 |
| 30代 | 370万円 |
| 40代 | 660万円 |
| 50代 | 1,000万円 |
| 60代 | 1,200万円 |



一般的には、中央値の方がいわゆる“ふつうの人”の実感に近いと言われてるよ◎
なので、自分に近い年代の中央値と比較することで、リアルな立ち位置が見えてくるかと思います!
毎月いくら貯めればいい?目安は手取りの○%
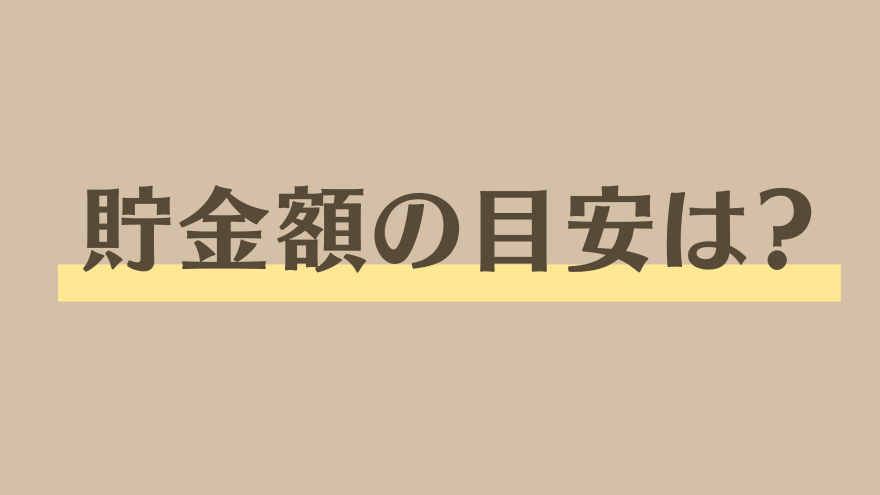
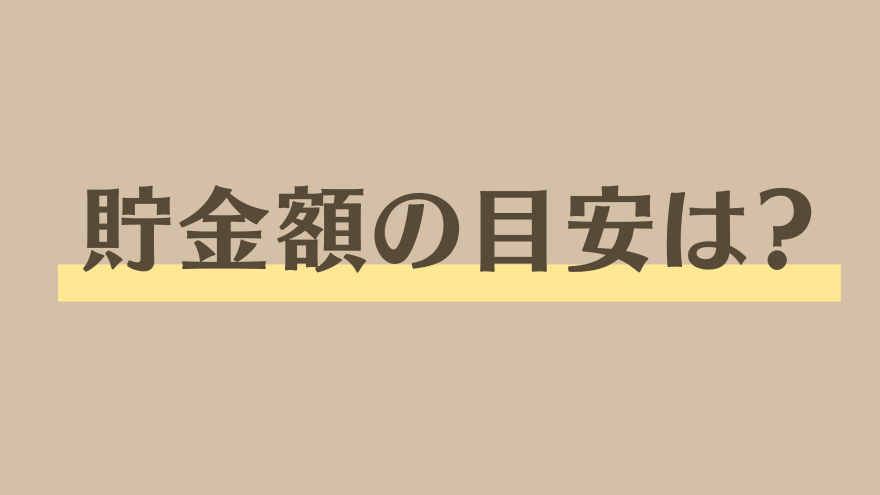
自分の立ち位置がなんとなく見えたら「これから毎月どれくらい貯金していけばいいの?」という疑問にたどり着くかもしれません。
よく使われる目安はコレ💡
- 手取りの10〜20%
→ 一人暮らしや、今はまだ余裕が少ない人向け - 手取りの20〜30%
→ 貯蓄ペースを上げたい、余裕がある人向け
たとえば、手取り20万円ならまずは月2〜4万円を目標にしてみるイメージです。
もちろん家庭の状況によって調整は必要ですが、「だいたいこのくらい」という幅で考えることがポイントです。
無理なく続けるためのお金の“仕組みづくり”
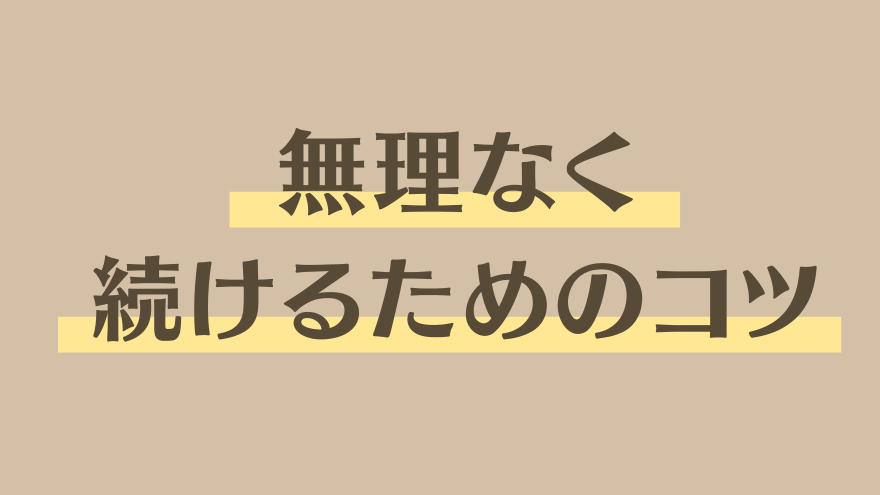
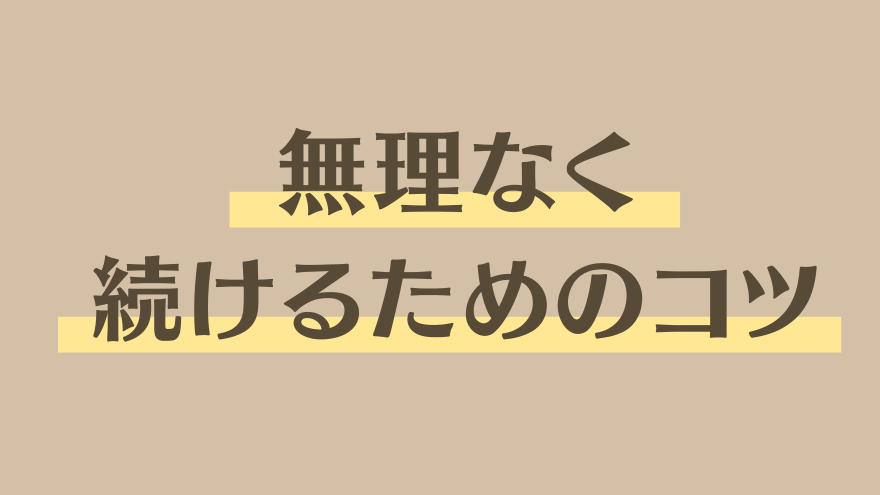
貯金って、我慢するものというより、仕組みで回していく方がずっとラクだったりします。
気合いでなんとかしようとするよりも、暮らしの中にうまく組み込んでおく方が、自然と長続きするんですよね。



そこでおすすめなのが以下3つの仕組みづくりです。
① 固定費を見直す
1度、固定費の見直しをし、月に支出を減らすという仕組みを作るだけでも効果はかなり大きいです!
毎月なんとなく払ってるサブスクや、内容が合っていない保険があれば、この機会に整理してみましょう。
② 先取り貯金を自動設定にする
「貯金は残った分で」と思っていると、なかなか貯まりません。
貯めておきたい金額を、先に別口座に分けておくことで“気づいたら貯まってる”仕組みを作ることができます。
③ 積み立て設定をする
NISAやiDeCoなど、制度としての選択肢は増えています。余裕があれば積み立て設定をし、自動で投資ができる仕組みを作りましょう!



特定の商品をすすめることはしませんが、知っておくだけでも「選べる力」になるよ◎
これらの3つを仕組み化することで、「頑張らなくてもお金が貯まる」流れを自然と作っていけます。
平均額より”自分に合う貯め方”を大切に!
「平均貯蓄額」って、数字だけを見ると一喜一憂しがち。ですが、実は調査の種類や世帯構成によって大きく違ってくることが分かりましたね。
今回ご紹介したように、
- 平均と中央値の違いを知って
- 自分の立ち位置をざっくり把握して
- 手取りの○%を目安に、ムリのない仕組みを作っていく
この”仕組みで回す”という考え方を、ぜひ覚えて実践してもらえたらと思います!



この記事が、これからの家計づくりのヒントになれば嬉しいな♪